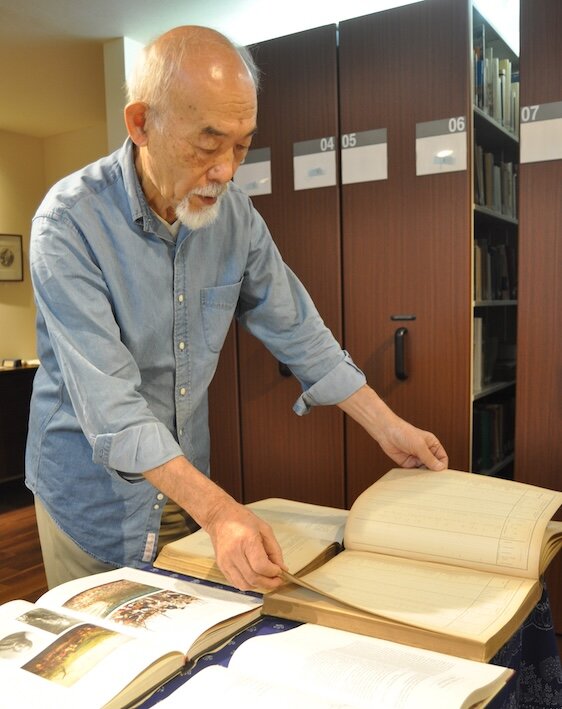議会ウォッチャーの4月メモ
広域連携・連合の中心となる佐久市で、市長と市議会議員の同時選挙が行われており、投開票日は次の日曜日に迫っている。
近年、防災、医療・福祉、ごみ処理、公共交通など、地域が抱える課題は複雑さを増し、もはや一つの自治体だけでは対応しきれないケースが目立つ。こうした背景から、自治体同士が連携して取り組む「広域行政」の重要性は、ますます高まっている。
このように、他の自治体の政策や選挙の行方が、当町の暮らしにも直接あるいは間接的に影響を及ぼす場面が増えている。だからこそ、近隣の選挙にも目を向け、関心を持つ姿勢がこれまで以上に求められる。
一方、町内に目を転じると、土屋町長が就任して3年目を迎えた。この間、町政はおおむね議会と協調しながら進められてきたように見える。しかし、ときに意見が対立するのは健全なことであり、むしろ必要な緊張感とも言える。
もし、町長と議会の間に意見の違いがまったく見られないとすれば、それぞれの立場から町の課題を真剣に見つめていないのではないかという疑念すら生じかねない。異なる意見が交わされ、議論が深まることによってこそ、多面的な課題の理解や現実的な対応策が導き出される。
こうした中、今月は町議会において、議長や各委員会の委員長などを選び直す改選期を迎える。これは町の意思決定の方向性に関わる重要な節目であり、新たなリーダーたちがどのような方針のもとで議会運営を担っていくのか、注目していきたい。
前回の改選から2年が経過する中で、遠山議長は「タブレット導入によるペーパーレス化」と「本会議のライブ配信」を所信表明の第1に掲げ、これを実現した。議会の様子が自宅からリアルタイムで視聴できるようになったことは、住民にとっても一歩前進と言える。町のホームページの刷新も相まって、情報公開の取り組みは着実に進んでいる。
ただ、「議会の活動が住民にはまだ見えにくい」との声も根強い。今後は、議論の過程や決定された内容を、誰にでも伝わる形でわかりやすく発信していく努力が、より一層求められる。
当町議会では「委員会中心主義」が採られており、政策や課題はまず専門の委員会で集中して議論され、その結果が本会議で共有される仕組みだ。これにより、深く実効的な議論が可能になる反面、委員会でのやり取りが住民に伝わりにくいという課題も抱えている。
今後は、委員会のライブ配信や全員協議会の議事録公開など、情報発信のあり方そのものを見直し、議会全体としての透明性をさらに高めていく必要がある。こうした取り組みが、議会に対する信頼の向上にもつながるはずだ。
町政は、町長と議会がそれぞれ独立した立場で役割を果たす「二元代表制」により運営されている。町長は政策の実行や予算の執行を担う「執行権」を、議会は条例の制定や予算の審議といった「議決権」を持つ。両者が対等な立場で緊張感を保ちつつ連携することで、健全でバランスのとれた町政が実現される。町の運営は議会の議決や承認を経て成り立つという制度の仕組みを、今一度確認しておきたい。
そして、町の未来を形づくるのは、町長や議員といった選ばれた代表だけではない。住民一人ひとりが日々の暮らしに関心を持ち、声を上げ、ともに考え、行動することが、まちをより良く変えていく原動力となる。選挙や議会の動きをきっかけに、政治をより身近なものとして捉え、持続可能なまちづくりへの一歩を踏み出していきたい。(文・赤井信夫)